幼児期のお子さんを本好きに!「読書習慣」を育む親の関わり方
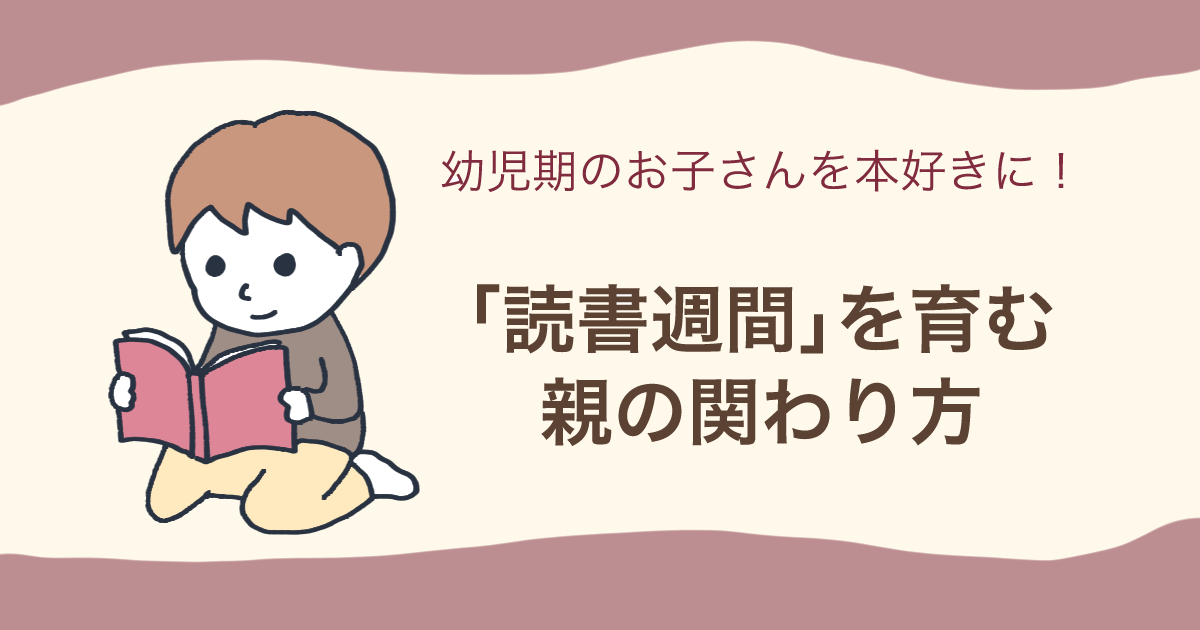
こんにちは!シバです。
「うちの子、好奇心旺盛でいいんだけど、どうせなら本を好きになってくれたら嬉しいな」
そう考える親御さんは、きっと多いはずです。YouTubeの動画がどこでも見れるようになった今、「子どもが本を読む機会が少なくなった」と少し不安に感じることもありますよね。でも、幼児期は「本好き」の芽を育むとっても良い時期なんです。
絵本は、小さなお子さんにとって、言葉や感情、そして新しい世界へと出会う「窓」。この時期に本に親しむことで、創造力、思いやる力、自分で考える力、そして何よりも「本を読むのは楽しい!」という思いが育まれます。
今回は、忙しい毎日の中でも無理なく、そして楽しく、お子さんを「本好き」に育てるための具体的なヒントをたっぷりご紹介します。この関わり方を実践すれば、お子さんの未来を彩る「読書習慣」が、きっと自然と身につくでしょう!
シバについて
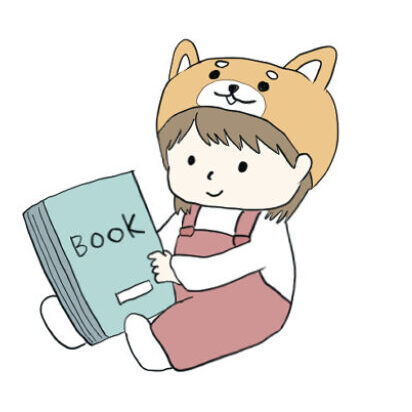
- ブログ×イラスト
- 1児のママ
- 年間50冊以上(週1~3冊ペース)
- スキマ時間=読書
- 読書大好き
なぜ「幼児期」に読書習慣が大切なの?
幼児期に本に触れることで、お子さんの未来は豊かになっていきます。
- 言葉の力
-
語彙力、読解力、豊かな表現力の基礎を育む。
- 考える力
-
想像力、集中力、論理的思考力の芽を育てる。
- 心の力
-
共感力、自己肯定感、感情を理解する力を養う。
これらの学力だけでなく、非認知能力(自制心、協調性など)へのいい影響もあります。また、親子で読み聞かせをする時間は、お子さんに愛情と安心感を与え、「自分は大切にされているんだ」「お母さんは僕のこと愛してくれている」と自己肯定感を育みます。
「本が好き」はこうして育つ!親ができる7つのこと
読書習慣を無理なく、そして楽しく続けるための具体的な関わり方を、実践的なヒントとして7つに絞って紹介します。
親がまず本を楽しむ姿を見せる
お子さんに本を好きになってもらうためには、まずお子さんの近くで親御さんが本を楽しむ姿を見せましょう。本のジャンルは何でもいいです。私は小説が好きなので、息子の横でよく推理小説を読んでいたり、仕事やヨシタケシンスケさんの本を読んでいます。
子どもの横で本を読んでいると「それ何読んでるの〜?」とよく興味を持ってくれるので、そこから一緒に絵本や図鑑を読み始めるときもあります。親が本に夢中になっている姿は、子どもの好奇心を強く刺激します。「ママは何を読んでいるんだろう?」「なんでそんなに夢中になっているんだろう?」と本そのものだけでなく、読書という行為そのものに興味を持ち始めます。これは読書を、単に勉強ではなく、「遊び」の一つとして認識することにも繋がります。
読み聞かせは「親子の特別な時間」と捉える
親の膝の上で、あったかい声を聞きながら絵本の世界に入るって、子どもにとって最高の安心タイムなんです。ぎゅっと抱きしめられたり、頭をなでてもらったり、そういうスキンシップって、「あ、僕って大切にされてるんだな」って心から感じられる瞬間。これが子どもの心の安定感とか、自分を好きになる気持ち(自己肯定感)を育む土台になるんですよ。
また、読み聞かせの時間をさらに快適にするために、温かみのあるブックライトを取り入れてみるもの良いですね。部屋が明るいと子どもがいつまでも寝ないので、部屋を暗くしてから手元だけ明るくして本を読んであげるときにピッタリ。
小さなお子さんの「選びたい」気持ちを尊重する
私は息子の「選びたい」「好き」な気持ちを尊重して絵本を選んでもらっています。読書を強制されると読みたい気持ちが出てこないので、息子が「これ読んでほしい!」と興味がある本を一緒に読んでいます。そうすると、集中力が途切れにくく、物語に深く入り込むのがわかります。
また、お子さんの「選びたい」「好き」を尊重することで、「自分の気持は大切にされているんだ」という自己肯定感が育まれます。お子さんとの会話を通して、絵本をきっかけに、お子さんの内面や新しい「好き」が見つかる機会にもなりますよ!
「読み聞かせ」は一方通行にしない
絵本を読むときに、文字だけを読んで一方的に話していませんか?読み聞かせは、ただ単に絵本を読むだけでなく、お子さんとお話しながら絵本をめくってみましょう。
何度か読んだことのある絵本でも、味方を変えれば違う楽しみ方もできます。イラストに注目したり、お子さんの好きなものを聞いたりすることで、親子でのコミュニケーションが育まれます。
毎日変化をつけながら読み聞かせするのも大変なので、親御さんの時間の余裕があるときに、お子さんと楽しみながら本を読んでくださいね!
「本のある環境」を整える
「本のある環境を整える」って聞くと、なんだか大変そうに聞こえるかもしれませんね。でも、これは全然難しく考える必要はありません!簡単に言うと、「子どもがいつでも、気軽に、ご機嫌で本を手に取れるような工夫をしてあげること」なんです。
「絵本は、読み聞かせの時だけ出す特別なもの」と思われがちですが、実はそうじゃありません。絵本は、おもちゃと同じように、子どもがいつでも手に取れる場所に置いてあげましょう。具体的には、リビングや子どもの部屋の低い棚に置いたり、絵本ラックに表紙が見えるように並べたりすると、子どもは「あ、これ読みたい!」とパッと手に取りやすくなります。
マガジンラックのように表紙が見えるようにおいておくと、お子さんの興味を引きやすくおすすめ。
図書館を「親子の遊び場」にする
「図書館」って聞くと、シーンとしてて「静かにしなきゃ!」と構えてしまいませんか?図書館は確かに本屋さんとは違い、大きな声で話したりはできませんが、本を無料で借りれる最高の場所です!本屋さんによっては、梱包されて購入しないと中身が見れない絵本があったりしますよね。しかし、図書館であれば、見たこともない図鑑や絵本が山ほどあり、本の中身に目を通してから借りることができます。
図書館では、自分で選んだ本を図書館のカウンターに持っていって、職員さんから本を借りる。これはお子さんにとって、ちょっとしたお買い物体験なんです。また、借りた本は、図書館に来る人みんなで読むものなので、汚さないように扱う。これも、本をより一層大切にする気持ちも育みますよ。
さらに、図書館は本を借りるだけじゃありません。読み聞かせ会があったり、子供向けのイベントがあるところもたくさんあります。「夏の暑い日は熱中症が心配だから、室内で過ごせるところないかな?」という方にはピッタリ。室内で涼しく、なおかつ親子で一緒に本んで過ごせる充実した時間になりますよ。
図書館をより楽しむためのアイテムとして、お子さんが自分で絵本を選んで入れられる可愛い図書館バックを活用すると、図書館に行くのが楽しみになりそうですね!
まとめ:本は、新しい世界へと出会う「窓」
今回は、子どもの「読書習慣」を育む親の関わり方についてご紹介いたしました。
幼児期の読書体験は、お子さんにとって一生の財産となります。大きくなってから「この絵本ママと読んだことある」「この絵本読んでるとき楽しかったなぁ」と思い出すたび、「僕って大切にされていたんだ」と子どもの安心感にも繋がります。親御さんの愛情ある関わりが、小さなお子さんを「本好き」に育てる大切なカギです。
親御さんも普段お仕事や家事で忙しいので、焦らず、親御さんとお子さんのペースで、親子の素敵な絵本時間をお過ごしくださいね♪
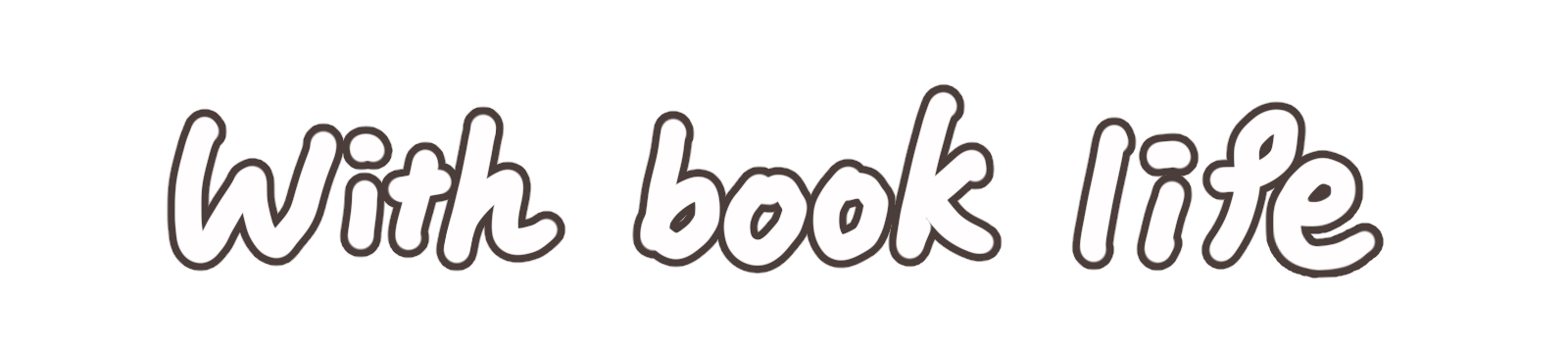

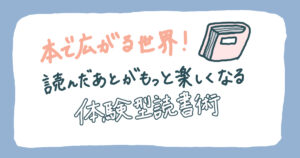
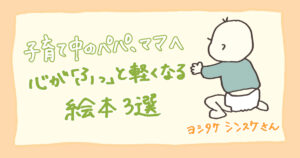


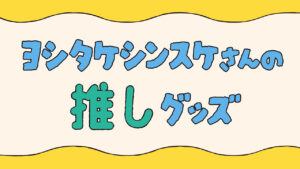
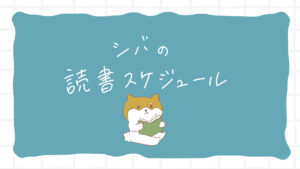
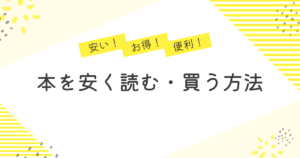
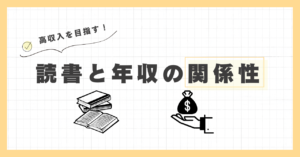
コメント